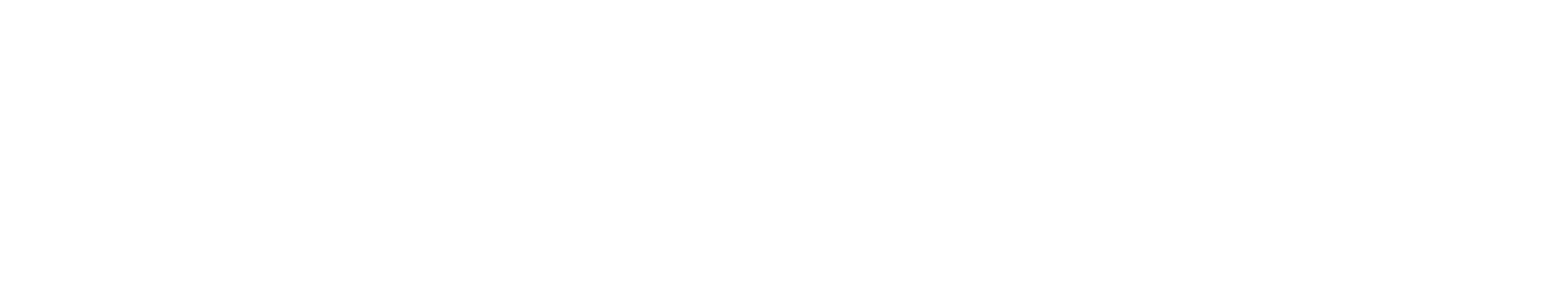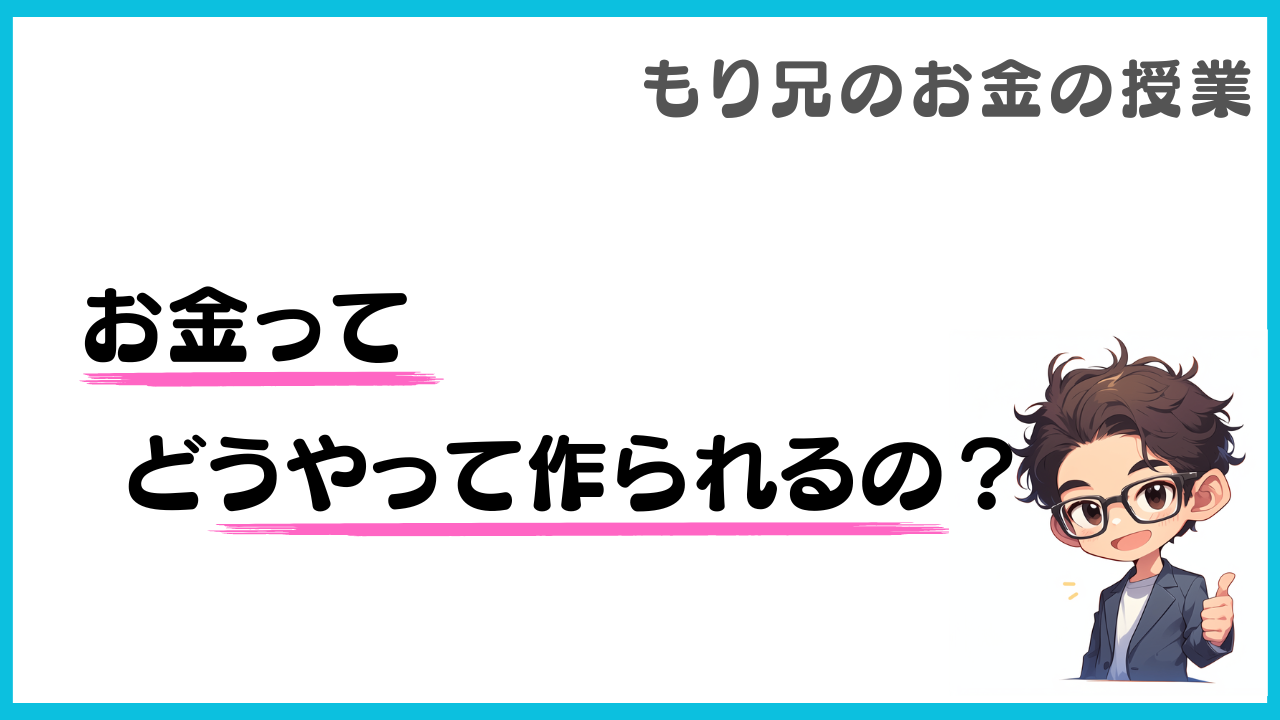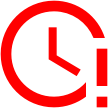こんにちは、もり兄です。
この記事は、「お金」という身近でありながら、意外と知られていないテーマを子どもと一緒に楽しく学んでいく内容です。
先生方に日頃の授業や朝の会、ちょっとしたお話の時間にご活用いただけるように作成しました。
この記事を読むことで、先生ご自身も新たな発見をされたり、教材研究のヒントを見つけたりしていただけたら嬉しいです。
さあ、お金の不思議を探究する旅に出かけましょう!
みんなは、お財布の中に入っているお札や硬貨を、当たり前のように使っているよね。
でも、このお札や硬貨って、一体どこからやってくるんだろう? どうやって作られているんだろう?
実は、みんなが使っているお札や硬貨には、すごいひみつがたくさん隠されているんだ。
今回は、そのひみつをたーぼ先生と一緒に探検してみよう!

今回のテーマは
「お金ってどうやって作られるの?」
みんながもっている「お金」の正体!
みんなが使っているお財布の中や、お家の人のお財布の中には、紙でできたお札と、カチカチの硬貨が入っているよね。
お店で物を買うときも、自動販売機でジュースを買うときも、このお札や硬貨が大活躍!
でも、このお札や硬貨って、一体どこからやってくるんだろう?そして、どうやって作られているんだろう?
実は、日本のお金は、とっても特別な場所で作られているんだよ。
お札をつくる「日本銀行」のふしぎ
まず、紙でできた「お札」から見ていこう。
みんなが使っている1000円札、5000円札、10000円札は、「日本銀行」という、日本で一番大きな銀行が作っています。
でも、日本銀行がお札をゼロから作っているわけではないんだ。
お札のもとになる紙を作って、絵や数字を印刷(いんさつ)しているのは、「国立印刷局(こくりついんさつきょく)」というところなんだよ。
日本銀行は、国立印刷局で作られたお札を、みんなの近くの銀行に送ったり、ボロボロになったお札を集めて新しいお札と交換したりするお仕事をしているんだ。
お札の紙は、普通の紙とはちょっと違うんだよ。
破れにくくて、水に濡れても大丈夫なように、特別な材料で作られているんだ。
だから、簡単にビリビリに破れたりしないんだね。
硬貨をつくる「造幣局(ぞうへいきょく)」のふしぎ
次は、カチカチの「硬貨」についてだよ。
1円玉、5円玉、10円玉、50円玉、100円玉、500円玉は、「造幣局(ぞうへいきょく)」という特別な工場で作られています。
造幣局は、大阪とさいたま(埼玉)、広島にあるんだ。
造幣局では、まず金属の板を丸い形にくり抜いて、それから、ギザギザのふちをつけたり、表や裏の模様をつけたりするんだ。
コインの模様は、日本の美しい風景や動物、植物などが描かれているものがたくさんあるから、じっくり見てみるのも面白いよ。
日本銀行のHPでは、お金がじっくり観察できるような「お金博物館」があるよ。
にちぎんキッズ(お金博物館)
偽物のお金を作らせないための工夫
みんなが安心してお金を使えるように、お札や硬貨には「偽物を作らせない」ための、すごい工夫がたくさんされているんだ。
例えば、お札には、
お札を光にかざすと、人物の絵や模様が浮き上がって見えるよ。
ホログラム
お札のキラキラした部分で、見る角度を変えると色や形が変わって見えるよ。
マイクロ文字
虫メガネで見ると、とても小さな文字が印刷されているのがわかるよ。
硬貨にも、同じ種類の硬貨をくっつけると音がしたり、ギザギザの数が決まっていたり、それぞれの硬貨に特徴があるんだ。
これらの工夫があるから、私たちは安心して毎日お金を使うことができるんだね。
日本銀行のHPには、他にもたくさんの「偽物を作らせない工夫」が紹介されているよ!
にちぎんキッズ(にせ札防止のひみつ)